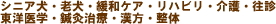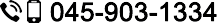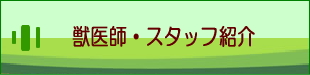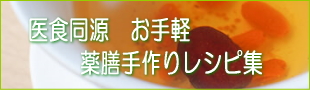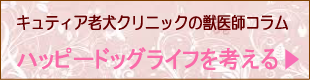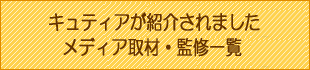八味地黄丸 はちみじおうがん

(ゴマノハグサ科カイケイジオウの花)
八味地黄丸は陰と陽から成り、生命活動を支える最も根源的な力である「腎精(じんせい)」の内の腎陽が不足「腎陽虚」に用いる「補陽剤」の代表方剤です。
漢方解説
【主治】腎陽不足(じんようぶそく)
加齢や生まれつきの腎気不足などにより腎の陽気が不足することで起きる冷え・腰痛・足に力が入らない等の足腰トラブルや、小便不利や頻尿といった排尿トラブルなどに用います。
【効能】温補腎陽(おんほじんよう)
東洋医学では、腎陽は元陽(げんよう)・真陽(しんよう)ともいわれ、身体全体の陽気の根源であり臓腑や組織を温めたり体液を動かしたりするとされています。
その大切な腎陽を補うことで本来の機能を取り戻すお手伝いをします。
【適応症状】
腰膝酸軟(ようしつさんなん)・四肢冷感
腎臓が腰の高い位置、脊髄の両側にひとつずつあることから「腰は腎の腑」と呼ばれており、「腎」の生理機能が失調すると酸痛(さんつう・腰のだるさや痛み)が生じます。また陽気不足によって動かす力や暖める力が働かず、手足の冷えや力が入らないといった症状が起こります。
小腹拘急(しょうふくこうきゅう)
「腎」より下部を温めることができなくなることで臍の下の筋肉が緊張し、硬く突っ張ります。
小便不利(しょうべんふり)・頻尿
体内での水液の貯留・分布・排泄の調整は「腎」の気化作用である「開合(かいごう・開は代謝による水液の排泄、合は身体に必要な水の貯留を指す)」で行われていることから「腎は水を主る(主水)」といわれています。
腎陽が不足することで開合が適切に行えなくなり、尿の排泄トラブルにつながります。
生薬配合
「君・臣・佐・使」の配合原則の意味を参照する【君薬】
附子・桂枝: 補腎気(ほじんき)温補腎陽(おんほじんよう)
附子(ぶし) 温裏薬。キンポウゲ科 烏頭aconitum car michaeli Debx.の子根。腎陽を益し、弱ってきた元陽を救うので、回陽救逆(かいようきゅうぎゃく)の要薬といわれる。

桂枝(けいし)辛温解表薬。クスノキ科の植物、肉桂Cinnamomum cassia Presl.。附子と配合することで温経通絡の効果で風寒湿痺による関節の痛みを取り除く。陽虚が極端に強くないときは肉桂を用いる。

【臣薬】
地黄(じおう):滋補腎陰
君薬の温める力を敢えて抑えることで「小火生気(しょうかせいき:少しずつ身体を温めて気を生成する)」という効果を得るために、君薬である附子と桂枝の8倍という多量を配合しています。
清熱涼血薬。ゴマノハグサ科の植物、地黄Rehmannia glutinosa Libosch.の塊上根。清熱涼血と強い養陰作用も併せ持つ。

山茱萸・山薬:滋補肝脾襲腎陰(じほかんぴしゅうじんいん)
陰中求陽(いんちゅうきゅうよう)。地黄という大量の補陰剤を用いながらも身体を冷やし過ぎないために、根幹に残った陽気を温める目的で配合される。
山茱萸(さんしゅゆ)収渋薬。ミズキ科の植物、山茱萸Comus officinals Sieb.et Zucc.の核を取り除いた果実。補肝腎作用もあるが、収斂固摂(しゅうれんこせつ)作用がつよい。

山薬(さんやく)補気薬。ヤマイモ科の植物、長芋Dioscorea opposite Thunb.の塊根。補腎・固渋の効能があり、腎虚による頻尿にも用いられる。

【佐薬】
茯苓・沢瀉:利水潤湿(りすいじゅんしつ)
腎陽虚により衰えた主水(しゅすい)機能を補う。
茯苓(ぶくりょう)利水滲湿薬。サルノコシカケ科 茯苓菌Poria cocos Woif.の菌核。体内の水が流れやすいように導く。その効能を強めるために沢瀉と配合して用いる。

沢瀉(たくしゃ)利水滲湿薬。オモダカ科の植物、沢瀉Alismatacea oriental Juzep.の塊茎。茯苓と同じ利水・滲湿効果がある。

牡丹皮(ぼたんび):清瀉肝火(せいねつしゃか)温補腎陽(おんほじんよう)
ボタン科の植物、牡丹paeonia suffiuticosa Andr.の根皮。虚熱(陰や血が不足することで身体に籠る熱)を冷ます作用があるほか、活血行瘀作用により血流を改善し瘀血を軽減する作用がある。

上記3種の佐薬を組み合わせた「三瀉(さんしゃ)」により、
・肝・腎・脾に水が停滞しないようにサポートする
・地黄や山薬といった大量の補剤による膩性(じせい。強い粘り気)が生じて消化器障害が起こることを防ぐ
漢方の古典にも記載されている
八味地黄丸は漢方の古典といわれる中国の医学書「金匱要略(きんきようりゃく)」に記載のある昔からある漢方薬です。
附子・桂枝・地黄・山茱萸・山薬・茯苓・沢瀉・牡丹皮の8つの生薬を煎じて粉にした後、蜂蜜を混ぜて丸薬として服用します。
獣医師 横山 恵理