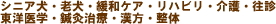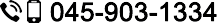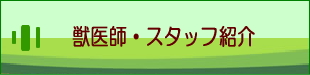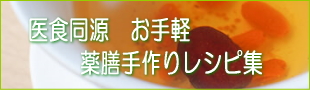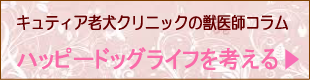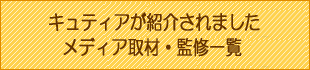二陳湯 にちんとう
 (半夏の原料となるカラスビシャク)
(半夏の原料となるカラスビシャク)主薬である陳皮と半夏が古いものの方が良質とされることから名づけられた、去痰剤の模範となる「湿痰(しつたん)」証の改善薬です。
漢方解説
【主治】湿痰(しつたん)
中医学では、生きていくうえで身体に必要な「水」の流れが停滞することで「痰飲(たんいん)」という病理産物となると考えられています。
粘調な性質のものを「痰」。さらさらしたものを「飲」とも区別します。「痰」は身体の中の正常な津液の流れを阻害してしまう為影響は多岐にわたる様々な症状を引き起こし、その性質によって湿痰・熱痰・燥痰・寒痰・気痰に分類されます。
二陳湯が適応となる「湿痰」は、「脾」の運化(うんか)作用の失調により生じます。
脾の運化とは食べ物の消化・吸収作用全般を指します。食べ物の栄養素とともに吸収された水分もこの運化作用により「肺」と「腎」へ送られ、それぞれの臓の働きで汗・尿となって体外に排泄されます。しかし「脾」の運化の機能が低下すると、水液が体内に停滞しジメジメドロドロとした「湿痰」になってしまうのです。
【効能】燥湿化痰(そうしつけたん)
体内にとどまる必要以上の水を排除して湿痰を取り除きます。
理気和中(りきわちゅう)
脾胃の動きと気の巡りを良くして水がとどまらないようにすることで湿痰を改善します。
【適応症状】
痰多痰白(たんたたんぱく)
『脾は生痰の源たり、肺は貯痰の器たり』
脾で生まれた湿痰が肺の働きを阻害することで多量の白い色の痰が生じ、咳につながります。この痰は喀出しやすいのが特徴です。
頭眩心悸(ずもくしんき)
湿痰が清陽の上昇を阻害して頭痛やめまい、動悸といった症状が現れます。
悪心嘔吐・腹部膨満(おしんおうと・ふくぶぼうまん)
湿痰が胃に停滞することで、胸やけや嘔吐、胃もたれなどの症状を引き起こします。
肢体沈運
余計な水が停滞しているので浮腫みが出て、身体が重だるく感じます。
生薬配合
「君・臣・佐・使」の配合原則の意味を参照する【君薬】
半夏;燥湿化痰(そうしつかたん)・和胃降逆(わいこうぎゃく)・止嘔(しおう)
サトイモ科、半夏 Pinellia temata Breit.の塊茎。
化痰薬。温燥の特性があり、湿痰を治療する際の要薬(ようやく・必須の薬)です。降逆和胃の効能もある為、胃気上逆による悪心嘔吐の治療にも用いられます。
生のままでは毒性が強く舌や口のしびれが生じてしまうので、一般には外皮を取り除いて乾燥し、炮制したものを用います。

【臣薬】
橘紅(きっこう);理気燥湿(りきそうしつ)・順気除痰(じゅんきじょたん)
ミカン科、橘Citrus reticulate Blanco及びその他同属植物の成熟果実の果皮である陳皮(ちんぴ)の特に古いもの。
理気薬。燥湿作用で半夏を助け、気の流れを整えることで痰を取り除く作用があります。また、制吐作用もあり、胃腸の蠕動も助けます。

【佐薬】
茯苓(ぶくりょう);健脾滲湿(けんぴしんしつ)
サルノコシカケ科、Poria cocos Wolf.の菌核。
利水滲湿薬。気を補い水を動かす。

生姜(しょうきょう);降逆止嘔(こうぎゃくしおう)
ショウガ科、Zingiger offcinale Rosc.の根茎。
辛温解表薬。半夏の毒性を抑制する他、半夏・橘紅の行気作用を助けることで消痰に働く。

烏梅(うばい);収斂肺気(しゅうれんはいき)
バラ科、梅Prums mume Sieb.et Zucc.の未成熟果実。
収渋薬。斂肺作用により咳を鎮める。
日本のエキス剤には配合されていないので、服薬する際に梅を水に溶いたものを使用するとよい。

【使薬】
炙甘草(しゃかんぞう);調和諸薬・潤肺和中
マメ科、甘草 glycyrrhiza uralennsis Frisch.の根。
補気薬。脾胃虚弱を補い、肺を潤す効果があります。緩和薬性、調和百薬の効能を持ち、様々な生薬の強すぎる作用を緩和することができます。

太平恵民薬局方に記載されています
「痰」による気血の巡りの停滞による影響は多岐にわたる為、六君子湯や抑肝散加陳皮半夏など、様々な効能の多くの方剤に組み込まれています。
獣医師 横山 恵理