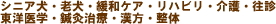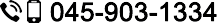「咳込みが増えた」というと、西洋医学では気管トラブルや心疾患が起こっていると想定することが多いです。しかし、東洋医学的には「肺」だけでなく「肝」「脾」「腎」といったほかの臓が原因となって起こることもあるとされています。西洋医学の薬があまり効かないし検査でも何も問題ないといった場合、実は原因が他にあるかもしれません。
「咳込みが増えた」というと、西洋医学では気管トラブルや心疾患が起こっていると想定することが多いです。しかし、東洋医学的には「肺」だけでなく「肝」「脾」「腎」といったほかの臓が原因となって起こることもあるとされています。西洋医学の薬があまり効かないし検査でも何も問題ないといった場合、実は原因が他にあるかもしれません。
咳嗽(がいそう)とは
東洋医学では咳や痰液を吐くことを主な症状とする病症を「咳嗽」と呼び、有声無痰のものを「咳」有痰無声のものを「嗽」と称します。
咳嗽の原因は大きく外邪(がいじゃ)による「外感」と身体の中の失調による「内傷」の二つに分けられます。
外感咳嗽(がいかんがいそう)
自然界に存在する、
・風(ふう)
・寒(かん)
・暑(しょ)
・湿(しつ)
・燥(そう)
・火(か)
の六種類の気候変化「六気(ろっき)」に異常が起きることで生じる邪気、「六淫(ろくいん)」に肺の経絡が侵されることで生じる咳嗽です。
その多くが新病(新たに発病した病気)になります。
風寒束肺(ふうかんそくはい)
風邪・寒邪が肺の経絡を塞ぐことで生じます。 重い咳声で白いサラサラした痰が出ます。鼻水・鼻づまり・発熱といった症状も。
風熱犯肺(ふうねつはんはい)
風邪・暑邪・火邪が肺の経絡を侵したり津液を傷つけて生じます。頻繁な激しい咳込みが生じ息が荒くなり、のどの痛みや発熱といった症状も。
風燥傷肺(ふうそうしょうはい)
風邪・寒邪が肺を傷つけ津液を消耗させて生じます。むせるような乾いた咳で喉がイガイガします。喉だけでなく唇や鼻の乾燥、喀樽出しにくい粘りけのある痰も。
内傷咳嗽(ないしょうがいそう)
臓腑機能の失調により起きる咳嗽です。「肺」の他「肝」「脾」「腎」が関わってきます。蓄積された消耗が原因となるので治りにくいのが特徴です。
肺陰虚(はいいんきょ)
肺が潤いを失ってしまうことで虚熱が生じ、肺内が焼かれて潤降作用(じゅんこうさよう)が失調することで起こります。空咳や痰の少ない乾いた咳が長く続きます。声が嗄れる、夕方ごろに微熱が出るといった症状が出ることも。
痰湿阻肺(たんしつそはい)
食べ物の消化・吸収を担う脾胃の運化作用が低下し、食べ物の栄養素とともに吸収された水分を体外に排泄するために「肺」や「腎」に送ることができずに停滞すると「痰濁(たんだく)」という病理産物が生じます。
この、脾で生まれた痰濁が肺の働きを阻害することで多量の白い色の痰が生じ、咳につながります。この痰は喀出しやすいのが特徴です。
肝火犯肺(かんかはんはい)
長期にわたるストレスなどにより自律神経のバランスが崩れることで肝と肺の気の流れが乱れて逆上し、止まらない咳や長引く制につながる。喉のつかえを感じることも。
ストレスがかかった時の他、寝起きや明け方に咳が出やすいのも特徴です。
肺腎気虚(はいじんききょ)
肺で吸入した空気は腎の納気作用によって身体の奥に収められます。この納気の働きが過労や体力の損耗によって弱まることで生じます。
「ハッハッ」とした少し苦しそうな浅い呼吸が特徴的で、ちょっとしたことでのぼせやすく、長引く咳につながります。

薬以外のアプローチも
以上のように咳の原因は多岐にわたるので、それぞれに治療方法も異なってきます。今回は一例として、肺腎気虚による呼吸トラブルが起きたジャック・ラッセルのゼン君での対応を紹介いたします。
梅雨明け後からの体調不良
18歳のゼン君は、膵外分泌不全による腹水トラブルがきっかけで去年の春からキュティアに通い始めました。鍼灸と漢方薬で腹水の心配もなくなり、認知症や後肢の弱りのケアをしながらマイペースに過ごしていました。
ところが、梅雨が明けて空気がカラッとしてきた7月後半頃から後ろ足のこわばりが強くなって車いすでないとしっかり歩くのが難しくなり、浅く速い呼吸でときおりむせるような咳が出るようになったのです。また、胸腹部の幅が広くなったようにも見えるため、飼い主さんはまた体のどこかに水が溜まってしまっていないかも心配されていました。
原因は腎と肺の疲れ
触診をしてみると、腎の弱りを示す「短脉」と骨盤の後傾の他、肋間筋及び横隔膜の緊張もかなり強いことが分かりました。7月のはじめの時はとてもご機嫌でそういった兆候はなかったため、急激な梅雨明けと猛暑で腎の「水」が枯渇したことが影響していると思われました。
その為に、後肢のトラブルだけでなく、「納気」の為に必要な横隔膜の動きも低下してしまった腎肺気虚の症状であると考えられました。胸腹部の幅が広がったように見えたのは、横隔膜の緊張が強すぎて胸郭が広がってしまっていたからだったのです。
鍼灸と経絡マッサージで元気に
あまりにも腎の弱りが強い場合は漢方薬の力も借りますが、ゼン君は「腎の水=陰」を補うことを意識した鍼灸施術によりその場で横隔膜の緊張と呼吸が改善したため、あとはおうちでの経絡マッサージをお伝えして毎日のケアに取り入れてもらうことにしました。
すると、呼吸や咳だけでなく筋力の衰えと思っていた後肢の弱りも改善し、今までのようにマイペースな徘徊ライフを取り戻すことができたのでした。
このように、東洋医学の診断、「証」に基づく治療は一見西洋医学的に見た症状とは関係ないようなアプローチで治療することも少なくありません。検査や投薬をしてもすっきり解決しない咳の時、少し検証してみてもよいかもしれませんね。
それではハッピードッグライフ♪
獣医師 横山恵理